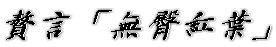

尻無川と大阪ドーム Mar.1997.
|
烏 斜日に輝き 斜日に輝き
鯔魚 晩潮に跳ねる
江村 暮景よろしく
釣り止んで なお橈を停む
|
このシリーズのなかでは最も愛すべき詩のひとつでしょう。季節は晩秋、淀川が海に注ぐ河口域の川のひとつである尻無川の堤には当時、黄櫨(はぜのき)が多く生じ、「紅葉の頃は、錦の色川水に映じ、瞻望また類なし。騒人・墨客多く舟行し、光景を賞す。(『浪華の賑ひ』)」といった名所になっていました。小竹は、大坂人には周知のこの黄櫨の紅葉に、さらに夕映えのイメージを重ねて、釣り舟から見る尻無川の景色を美しく詠っています。夕方の満ち潮に跳ねる鯔、そして夕映えに包まれながら静かに暮れていく江村。一つひとつは漢詩に常套的な道具建てですが、それぞれのイメージが溶け合って調和的な風景が描きだされています。そして、それらの光景を眺める釣り人の視点を取り入れた第4句が、詩に奥行きと余韻を与えているようです。
ところで小竹の頃の大坂と現代の大阪を比べた時、最も変化の(あるいは風景破壊の)度が大きいのは、この尻無川をはじめ、安治川・木津川の三川が当時、広々とした新田地帯を潤していた淀川の河口域だといえるかもしれません。近代の東京・大阪に勃興した重工業とそこで働く人々の拠り所となったのはこの河口域であり、最近の“ウォーターフロント”などという不動産屋のイメージ操作にも関わらず、そこには殺伐たる大小の工場や港湾施設、密集住宅などが無秩序に集中し、100年の工業化の汚れが拭い難く堆積しています。秋に赤く色づく黄櫨どころか、川沿いに緑を見ることさえそこでは難しいのです。しかも、海を埋め山さえ崩す工業化の蛮力の前に、川が恙なく存在している保証はありません。尻無川も然り。古い地図を頼りに、江戸期に尻無川沿いの名所として名高かった竹林寺や茨住吉神社を訪ねてみたところ、そこは市街地のただ中。いつ埋め立てられたのか、尻無川の流れは消えていました。古今の地図を比較してみると、生き残ったのはどうやらかつての後ろ半分だけのよう。わずかに残った流れの岸に立ってみると、かつて川が続いていた方向には、巨大な銀色の蛸みたいなドーム球場が、あきれるほど現実離れした姿で立ちはだかっているのでした。
|