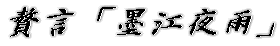

住吉公園の松 Mar.1997.
|
海上 秋雲暗く
祠頭 暮雨頻りなり
夜 松際の路を行けば
時に点灯の人に遇う
|
住吉大社のあたりは、古代にはすみのえ(住江あるいは墨江と表記)と呼ばれ、重要な港だった土地です。しかし、海外交通の玄関口として遣唐船が船出したこの港も、中世には淀川の運ぶ土砂によって埋まり、港としての機能を失ってしまいます。そして、江戸時代には現在と同じように、住吉大社の鎮座する名所としてのみ名高かったようです。もっとも、埋め立てによって海岸線が遠ざかった現在とは違い、当時は太鼓橋を渡って一面の松原のなかの参道を西に歩けば、鎌倉末期に灯台として作られたという大きな高灯籠があり、その向こうには遠浅の砂浜が広がっていました。浜には茶屋が並び、季節には潮干狩りの人が出盛ったようで、住吉は白砂青松をもって鳴る行楽地でもあったわけです。小竹もこの詩に海浜の風景を盛り込んでいますが、それはそぼ降る夕暮れの雨のなかの情景。月並みな白砂青松の叙景を避けたところに、詩人としての工夫が感じられます。小竹には、ほかにも「墨江遇雨」という詩があり、あるいは住之江と雨とは、この詩人にとって切り離しがたいイメージとしてつながっていたのかもしれません。
低く垂れ込めた秋の雲、暮雨、灯をかかげて歩く夜の松原――そんなしぶいシチュエーションが似合った当時の住之江。しかし今、そんなイメージをもってここを訪れた人が味わうのは失望以外の何物でもないでしょう。海がはるかに遠ざかったことは既にいいました。住宅やマンションが周囲に立ち並び、道路を疾走する車の騒音が波音の代わりに常にとどろいていることも、日本中の都市の文化財がそうなのですから、致し方ないことでしょう。松原のなかを貫いていた参道は、今は市民公園になっています。それはそれで結構なことなのですが、我慢できないのはそこに洋風のペーブメントが敷かれ、緑の相談所とやらができて、パンジーとかロベリアが植えられた花の道が出現していること。今も道の両側に立ち並ぶ年古りた石灯籠を取り囲むのは、松の濃緑(こみどり)ではなく黄色や赤のパンジー。ああ、なんという不調和でしょう。現代日本人の美意識がこの程度のものだとしたら、何ともなさけない限りです。そして、あれほど豊かだった(「浪華名所図鑑」を参照してください)松はどこへ?住吉大社の鳥居前から高灯籠まで、街路樹ばかりがめだつ参道を花から目をそむけながら歩いて、やっと一本見つけた老松。それは、かつての清遊の地のその後の成り行きを示すように、大きく傾いた姿をさらしていました。
|